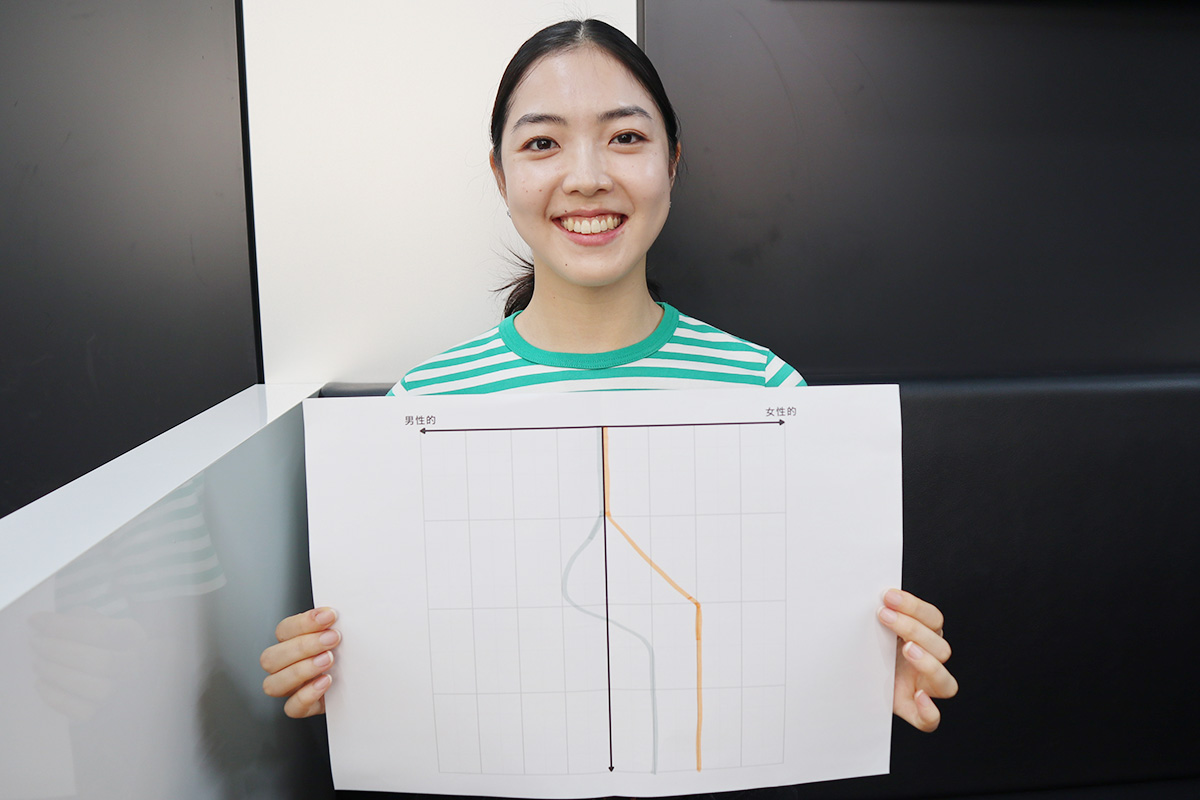
1997年千葉県生まれ。IT系会社勤務。趣味は本を読むことと、旅行をすること、寝ること。
「女性は家庭的なほうがいい」という価値観を感じ始めた思春期
女子大学生として括られ、ギャップに苦しんだ学生時代
大学卒業後の留学や旅行で触れた世界の価値観
大人になった今、他者との価値観の違いにうまく順応していけるようになった
留学経験もあり、旅行好きなみきさん。日本を出た先での貴重な経験と新たな価値観の発見のコツを伺いました。
留学は時期は大学生時代ですか?ちなみにどこにいったのでしょうか?
いえ、学生時代ではなく、卒業後に就職せず留学に行きました。一応新卒採用で内定をもらった会社があったのですが、結局、内定は承諾せずにデンマークに半年間留学し、そのあと1年間ワーキングホリデーでオランダに行きました。
就職をしなかった理由は何かあったのでしょうか?
就職しなかったことも性のゆらぎと若干リンクしていますね。新卒時期の就職活動は会社から自分自身の中身を見てもらえているというよりは、 「◯◯大学の◯◯学部の、◯◯の経歴の見た目の女性」といった、所属や外見で見られているなということを感じてなんとなく嫌悪感がありました。その上、あまり自分がやりたいこともわかってなかったということもあります。
新卒で入社するというのは、初心者に向けて、色々手取り足取りお世話をしてもらえるという、すごく貴重な経験ですごく大事なことなんだなというのは今となってはわかるのですが、 その時はその価値がわからず、「とにかくいやだ!」、「この居心地の悪さから逃れたい!」というところがありました。
留学はずっとしたいと思っていたのですが、大学が栄養士の資格を取れる専門課程だったので、その途中で課程を抜けて留学するという制度が用意されておらず、ずっと行きたいなと思いつつもできなかったんです。「ここでしなければ一生しないだろうな」と思い、留学することにしました。
思い切った決断ですね!ヨーロッパなどは日本より多様性の理解が進んでいると思いますが価値観の違いは感じましたか?
価値観は違います、全然違いますね。それこそヨーロッパの中でも、北欧とか北ヨーロッパはすごいオープンな国民性というか、全裸の女の人がいたりもしました。(笑)
え!プライベートビーチとかではなくですか?
プライベートビーチとかではないです。本当はダメだと思うのですが、私が行っていた学校には私有の山があって、そこを裸で駆け回る女の子たちがいました。活気やエネルギーが溢れた女子生徒が多くて、アスリートでもない普通の女の子でも180cmを超えるぐらいの体格も珍しくはないので、男子生徒とやり合うバイタリティやその雰囲気に圧倒されました。「強い女かっこいい!」というものがありましたね。
日本ではエネルギーが溢れているような振る舞いをしていると「女を捨てている」といったことをよく言われますが、彼女たちはそんなことはなく、フェミニンなドレスも着るし、女性であることもちゃんと楽しんでいる印象がありました。そういうのは日本にあまりないなと感じました。
日本でいう女性らしいって、立ち振る舞いが上品で、おしとやかで…というような印象で、そういう振る舞いをできる人がモテる、といった型にはめられているけれど、海外は色んな人がいるということが前提になっているなと感じます。
確かに男女の体格差は対等な関係性の構築に関係しているのかもしれませんね。日本は男女間での身体の差が大きいので、物理的に力も強い相手に対して事を荒立てない考え方があるのかもしれません。
確かにあるかもしれません。でもヨーロッパにも差別が全くないわけじゃないです。男女差別というのは日本よりも少ないと思うのですが、人種や移民に対しては、ある程度の人種差別があります。露骨に差別する人は今はあまりいないと思うんですが、隣の部屋や家に特定の人種の人が引っ越してきたら嫌だ、という発言をしていたり、人種によって給料の差、就職できる仕事の差があるといった潜在的な差別はまだ全然あると思います。
でも、男女の話に戻りますが、ヨーロッパでは女性が「男女みんな同じだ」、「お前の母親も女だろ」ぐらいの勢いで女性自身が積極的に平等を勝ち取りに行っている側面があり、そういったところは日本と違うかなと思います。
留学前に感じていた、女性としての見られ方への反発という気持ちに変化はありましたか?
社会から求められる女性像に苦しいと感じていたのですが、今はそれに応えなくてもいいんだ!ということがわかりました。自分が好きなようにしていいし、好きに生きていいんだという意識になったと思います。
それを知れた1番大きなきっかけとしては留学の経験でしたが、私は旅行も好きで、旅行に行くだけでも様々1価値観を知ることができ、自分の固定観念の呪縛を解き放つ良い方法だと思います。
1つの社会しか知らないと、その社会の期待に応えないといけないと追い詰められると思うのですが、違う価値観で生きている人をちょっと知るだけでも、 これに応えないことは世界の終わりじゃない、という意識になれると思います。それは、性自認や女性であることのプレッシャー以外にもいろいろなことに対して気が楽になったことではありますね。
旅行でも新しい価値観を知ることができるのはなかなか新鮮です。一方で留学よりも期間が短いので体感がしにくいのかなとも思うのですが、何か旅行の際に意識していることはありますか?
人間観察がとても好きなんです。例えば電車で「あの人今座れなかったな」とか、「あの2人の関係はどういう感じなのかな」と想像したりしているのですが、それが違う国だと、人々の振る舞いが自分の想像とは違うことも多く「それをそうするんだ!」ということあって、結構面白いです。
あとは「旅の恥はかき捨て」、じゃないですけど、私はカフェや街中で自分から話かけます。店員さんにおすすめを聞いたり電車で隣に座った人とちょっと喋ったりとかします。日本ではあまりないですけど、特にヨーロッパとかだと普通にある光景かなと思います。
それはすごいですね!電車で隣の人にはどのように話しかけるのですか?
まず物を褒めるんです。「そのリュック可愛いね」とか、なんでもいいです。そうすると大体「どこから来たの?」となるので「日本だよ」と伝えて「日本行ったことある?」というような話に展開します。さらに「どこどこ行くといいよ」と話題を振っていきます。話しかけるのは多少勇気が必要ですが、普段と違う自分に頑張ればなれるんだと思います。
なるほど!とっても穏やかな語り口調のみきさんですが、元から社交的ですか?
全然ちがいます。今だに両親にいじられる小学生時代のエピソードなのですが、スーパーでレジ袋に物を詰めていて、もらっていた枚数で足りなくなってしまった際に、店員さんに追加のレジ袋をもらいに行けなかった経験があります。もう会計が終わったのに「レジ袋ください(※当時レジ袋は無料)」と言うのがちょっと恥ずかしかったのか、 知らない人に話しかけるのか恥ずかしかったのか…それくらいにはシャイで人見知りでした。
あとは昔から完璧主義というか、 自分の恥ずかしい部分を見せるのがすごく苦手だったんです。道でつまづいたところを人にみられるだけでもう赤面で家に帰りたくなるというような。でも、成長する過程でいろいろな経験をしていくうちに、自分の恥ずかしいことや失敗をちょっとずつ許せるようになりました。海外での行動は「まあせっかく遠いところまで来たなら何か得て帰らなきゃ」という意識もあるかもしれませんね。

インタビューを通して、ラベリングされることに生きづらさを感じていた印象が強いみきさん。今思うジェンダーの悩みはあるのでしょうか。また、ラベリングが残る社会に対してどう思っているか伺いました。
現在思う女性であるがゆえの悩みなどはありますか?
キャリアと妊娠・出産について考えます。ぼんやりと子供欲しいなとは思っていて。例えば転職したいなと思っても、転職してすぐに子どもを産むというわけにはいかないから1年ぐらい働いて産休取れるタイミングで…という段取りをイメージしますよね。そうするとじゃあ転職するタイミングとはいつになるんだ?という感じです。
こういった悩みは男性と比べると少し不公平だなと思います。男性だったら、結婚しようが、 子どもが生まれようが関係なく仕事を続けられるし途切れがないことが多いですよね。最近は育休を取得している人も多くなってきたのかなと思いますが。
子どもを作るにしても年齢的な部分のリミットは意識せざるをえないので、きっちり人生設計をしなくてはいけない意識になりますよね
子育ては一度始めたらやめられないので覚悟が必要ですよね。今はリミットに関しては卵子凍結などがありますが、そこまでの費用と労力をかけて、子どもが欲しいのかと言われるとわからないという気持ちになっています。
私がこのようなことで悩んだ時に、同じ状況にいるだろうなという友人に相談しようと思ったのですが、その友達が意外に私と考えていることが異なり、自分の相談したかったことができなかったことがあります。パートナーがいて、仕事をそれなりにしていて結婚を考える年代に入ってきた似た境遇の人でも、同じように世界が見えてるわけじゃないので、誰かに相談するのもなかなか難しいと感じます。
まだまだ社会には様々なラベリングが残っていると思うのですが、今改めてラベリングについて感じることはありますか?
私も含めラベルのことをみんな気にしすぎだと思います。ラベルを貼っても結局は人じゃないですか。1人1人の人間です。一応生物学的には女性、男性という型も必要だとも思いますが、一方で多様なセクシャリティの人がいて、ラベルを貼ったとしてもどのみちその人を見る必要があると思うんです。シンプルに「その人」を見ることができる人になりたいと思っています。人との関係を築くときは先入観を入れないで話せる人になりたいです。
そして、ラベリングは違和感を抱えている人一人一人が心掛けないとなくならないような気がします。例えば、古い価値観の人がどんなにその価値観を押し付けようとも、私たちが「私はその価値観では判断しない」という態度で示して、 その押し付けているラベルが無意味ということを気づかせるしかラベリングはなくならないのではないかと感じています。
一方で、どんな人にも培ってきた人生経験があるので、その感覚を時代と違うから今すぐ捨てろ、変えろということも酷かなと思います。だから新陳代謝のように、少しずつアップデートしていけばいいと思います。
新陳代謝というのは面白い表現ですね
「そう思っている人もいるよね」と聞き流せるメンタルは必要だと感じます。「あなたはあなた、わたしはわたし、だけど、一緒に日本に住んでいますね」ぐらいの意識じゃないと自分らしく生きていくことは無理だと思います。違う価値観の人のことを嫌うことは簡単かもしれないけど、そうではなく、理解するためにはそういった心構えでいる必要があると考えています。
許容するマインドはとても参考になります。最初の方にお話しされていたご両親との女性としての生き方の価値観の違いもこのように受け入れているのでしょうか?
そうですね。両親の人生をリスペクトしたいと思っています。特に母は若い時に母 (みきさんの祖母)を亡くしていて、父(祖父)と兄(叔父)を支えていて、結婚してすぐ子供ができて、「家族を支える人」という役割になった。そういう人生も尊重したいと思います。だから「母の生き方や価値観」をリスペクトしているのですが、でもその生き方では自分は満足できないかもしれないとも思っているので葛藤しますし、難しいです。
ご両親だけではなく、同世代で親しい人との価値観のギャップを感じた時や仮に感じた場合の向き合い方や考え方はありますか?
例えばパートナーなど、このままずっと一緒に生きて行くことを考える人だったら、どうしてそういう価値観なのかというのを掘り下げて理解したいなと思いますね。全然理解できない人とは一緒にはいられないなとは思います。
でも、友達だったら全然気にしないです。「あなたはそういう考えなんだね」と思うだけです。私は話すトピックが友達ごとに違っていて、この子とは好みが似ているから趣味についてすごく話すとか、この子とは人生観についてすごく話すとか、 結婚とか恋人系の相談はこの子…というような接し方をしているので、友人のなかでも様々な価値観があるなと思います。仮に価値観が合わなくても、その側面では合わないけど、じゃあこっちの側面では合うかな、といった見方をしていますね。例えば、「そんな生き方はあなたらしくない!」と感じることがあっても求められてなければ伝えるのは違う気がします。その人からしたら、私の人生なんだから勝手にさせてよとなりますよね。
お話を伺っていて、ラベルは窮屈な部分がありつつも、その窮屈さをきっかけに行動をして新しい価値観を広げていけることができるのかもしれないと感じました。「意見が違っても共存して生きていく」という自分なりの答えを見つけていくイメージですね。
そうですね。自分以外の価値観や考え方って変えられるものじゃないと思っています。受け入れ方を知るしかないということはちょっと悲しい気もしますし難しいテーマなので今すぐ結論が出ることではないと思います。ただ、私が最初に女性というラベルの違和感を感じたのが両親からだったので、なんとか自分の中で折り合いをつけた答えがこの考え方だと思います。みなさんの参考になれば嬉しいです。
