プロフィール:福岡県育ち IT系会社勤務。フリーランスで動画編集・アニメーション制作など。趣味は読書と映画とラグビー観戦。
女の子らしい見た目で違和感もなかった。おもちゃなどの好みは女児向け男児向け関係なく好んでいた。
今までは、自分が同姓を好きになるなんて思いもしなかったが、同性の先生に好意を抱く。その時は男性目線で意中の相手を見ていた。
大学入学を機に、今までとは違う新しいタイプの人とも接するようになり、ファッションにも変化が。しかし周りに合わせながらも徐々に違和感を感じるようになり、様々な格好を試してしっくりくる形を模索する。
性別の押し付けを嫌いながら、相手の性別によってコミュニケーションの方法を変えており、自分の中の潜在的な固定概念に気づく。
ノンバイナリーを経て、今は女性であると感じているが、その感覚にはグラデーションがあり、100%ではない。
大学へ進学をきっかけに様々なファッションを通し、「しっくりくるスタイル」を見つけます。同時に自認とファッションは切り分けられると気がついたそうです。
大学進学後、ファッションや外見について大きな変化があったのでしょうか。
大学に進学して一人暮らしを始め、アルバイトでこれまでよりも自由にお金が使えるようになり、美容室に通ったり、服を買ったりすることが増えた影響なのか、明確なきっかけ不明なのですが、見た目に大きな変化がありました。元々ショートカットか長くてもボブの長さだった髪を5年程度伸ばしてパーマをかけて、特に20代前半はギャルっぽい見た目をしていた時期がありました。めちゃくちゃ見た目がギャルだったんです!
えー!想像がつかないです。
自分がどのような格好が好きなのか、自分らしいと感じるのかがよく分からなくて。今振り返ると、かなり迷走していた時期だったなと感じます。オタク時代からのギャップが本当にすごくて、それまではユニクロの服で落ち着いた見た目だったんですが、大学で様々な人がいる中で『あの人おしゃれだな、ああなりたいな』と考えるようになり、シンプルに興味がおしゃれに向いたのだと思います。
当時、私は美術サークルに入っていて、相変わらず大学でも絵を描き続けていたんですが、大学には同じ美術系でも『美術サークル』と『漫画研究会』の2つがあり、漫画研究会はもうオタクしかいない中学校の頃の延長といった感じだったんですよ。ですが、美術サークルは結構シュッとしていて、逆に『私たちはオタクじゃない』というアイデンティティが強かったんですよね。 目指す先はクリエイターなんだという感じで見た目もおしゃれに見えるように気をつける、という人が多かったです。 その影響もあるかもしれません。
ギャルというと女性らしい格好のイメージがありますが、内面とのギャップはありましたか?
ギャルの見た目に振っていた時は、自分の中で、そこまで女性性のようなものは持っていないな、と感じて結構ギャップがあったんです。 見た目は超ギャルなんですが、本当にこんな格好したいんだっけ?と思っていました。
考えると友人に合わせてギャルっぽい格好をしていて、自分自身もそれはそれで楽しんでそのように服装を決めていましたが、例えばギャルの友達とクラブに行ってもすごく浮いていて、 全然楽しく感じませんでしたし、クラブ行くならコミケとかに行っていた方が楽しいと思っていました。お金払って何しているんだろうと感じて、この格好とかも多分合ってないのだろうと思っていました。
更に30代手前ぐらいで、10kgくらいダイエットをしたら、着る服が変わったこともあり、見た目も変化しました。そのタイミングでコスプレをしてる友人から”ナベシャツ”(※胸の膨らみを抑えて目立たなくする服)の存在を教えてもらって、別に胸を隠したいというわけではなかったんですが、ボディラインを変えられるということが面白いと思って活用するようになりました。 ペタンとした感じのシャツの着こなしやシルエットがすごく好きだったので、痩せたタイミングということもあり、ボーイッシュというかメンズライクな服を着るようになったら、それにハマったという流れですね。髪も短くしました。
見た目の変化で周りからの見え方も変わっていきましたか?
はい。例えば新宿などを歩いていると、キャバクラの呼び込みの人たちから『お兄さん、いかがですか?』と声をかけられることが増えて。自分ってそこまで男性的に見えているんだと気づいた時、この振るまいの方向性の方が自然かもしれないと不思議と居心地の良さを感じました。この時期はかなり男性性に寄っていて、髪型もツーブロックでしたし、スカートも履けなかったくらいです。女装しているみたいで気持ち悪いと感じていました。
ノンバイナリーかもしれないと気付いたきっかけはありますか?服装が大きいのでしょうか?
時代が進んでいくとLGBTQなどある程度まとまった情報が出るようになり、それを読んで今までよくわからなかったものが、実は名前が付いてるのだと知ることができました。 性自認と社会的な見え方、見せ方を切り分けただけで、こんなにすっきりするのだと感じました。例えば社会的に『こうみられたい』というものがある場合は、服装とかファッションで変えられるという理解ですね。女性的な格好をするときもあるし、中性的な格好をするときもある。 性自認と性表現(どうみられたいか)は切り分けて、自分が中性的になっているというよりも、どういうふうに見せるのかを調整していると切り分けて考えられるようになりました。
今は今までで一番落ち着いていると感じますし、グラフの線も真ん中で落ち着いています。服装についてもボディラインが出ないものであればロングスカートも好きですし、化粧もそれなりに好きな範囲でします。

性別のラベリングを押し浸かられたくないと思う一方で、恋愛になると相手の性別によってコミュニケーションの仕方が変わってしまうというまりぃさん。良くないと思いながら、そう思ってしまう起因を紐解きました。
見た目の部分も男性的になりつつ、性自認の部分も中心に寄っていますね。
この辺は言語化が難しくて、両方やってみて、探す、試すという感覚だったと思います。私はバイセクシャルなので、過去には男性とも女性とも付き合った経験があるのですが、振り返って考えると、相手の方の性別によって自分の振るまいが変わる気がしていています。その人のタイプで振る舞いが変わるというわけでも無くて、例えば決断力があってリードしてくれる女性でも共通して『女性と付き合う振るまい方』になりますし、おとなしくて控えめな男性でも『男性と付き合う振るまい方』になります。
ご自身の“男女としての役割”が相手の性別によって変わるということですか?
これが本当に難しいのですが、一概に女性と恋愛関係になるときは男性らしく振るまうということではなくて、相手の女性がフェミニンな人か、中性的な人かでそこも変わるのですが、コミュニケーションの仕方が変わるという感じが近いと思います。全般的に相手が女性の場合、相手に対してものすごく丁寧に接するというか、自分の言葉が相手をにとってどう捉えられるか、細かく考えるようになり、『これは今言うと良く無いかも』などと考えて遠慮がちになります。
一方で、相手が男性の場合は、そこまで考えずに思ったことをバーっと言っちゃう感じです。その後どのような反応があっても、反応があってから考えれば良いという付き合い方になるんです。
なんとなくわかります。振るまいというよりもコミュニケーションの方法を相手の性別で切り替えているということですね。
確かにそうかもしれません。それは仕事や人間関係の中でも通じている部分がありますね。例えば、職場で女性の同僚や上司と接するときは、自然と『嫌われないようにしよう、みんなと仲良くしよう』という気持ちが働いて、女性のコミュニティでは特に気を遣っています。ですが、相手が男性の場合は、嫌われてもいいやと考えて思ったことはズバッと言っちゃうという付き合い方になります。
この違いは自分でも明確にはわからないのですが、考えてみると自分の中にステレオタイプな考えがあるのかなと思います。よく女性の方が社会的コミュニケーションスキルを持っていてコミュニケーション能力が高いと言われているイメージがあります。みんなで協調したり、その意見をまとめたりするのが比較的上手ということで、それは生まれ持った性質的にそうかもしれませんが、女性がそういうふうに育てられているという部分もあると思うんですよね。 私はすごくそれを感じていることもあり、女性のグループだとみんなで意見をまとめて嫌われないようにしようという意識が強く発揮されるんです。恋愛でもそうで、まずは相手の話を聞こうとなるのですが、男性のグループはそういうことが無いんですよね。
その差は面白いです。女性の方が結婚、出産、単身で生きる選択など人によってはセンシティブな話になるため傷つけないようにするという意識が働くのでしょうか?
今、その質問を聞きながら思ったのは、多分私は女の人と仲間だと思っているんですよ。女性という集団に私は所属しているから、理解できるはずという意識です。例えば同じムカつく上司でも、女性の上司には『この人にもいいところがあるかも』『この人にはあの時いいことをしてもらったしなあ。』 などポジティブな評価をしますが、男性の上司に関しては『この人と私関係ないし』と捉えてしまいます。女性上司に対して言えないのは多分、私がその女性という所属集団の中にいるから、多分そこから追放されたくないという感覚に近い気がします。あとその所属意識から、心の中で女性に対しては対立していても、話せば理解してもらえると感じている部分もあるかもしれないですね。
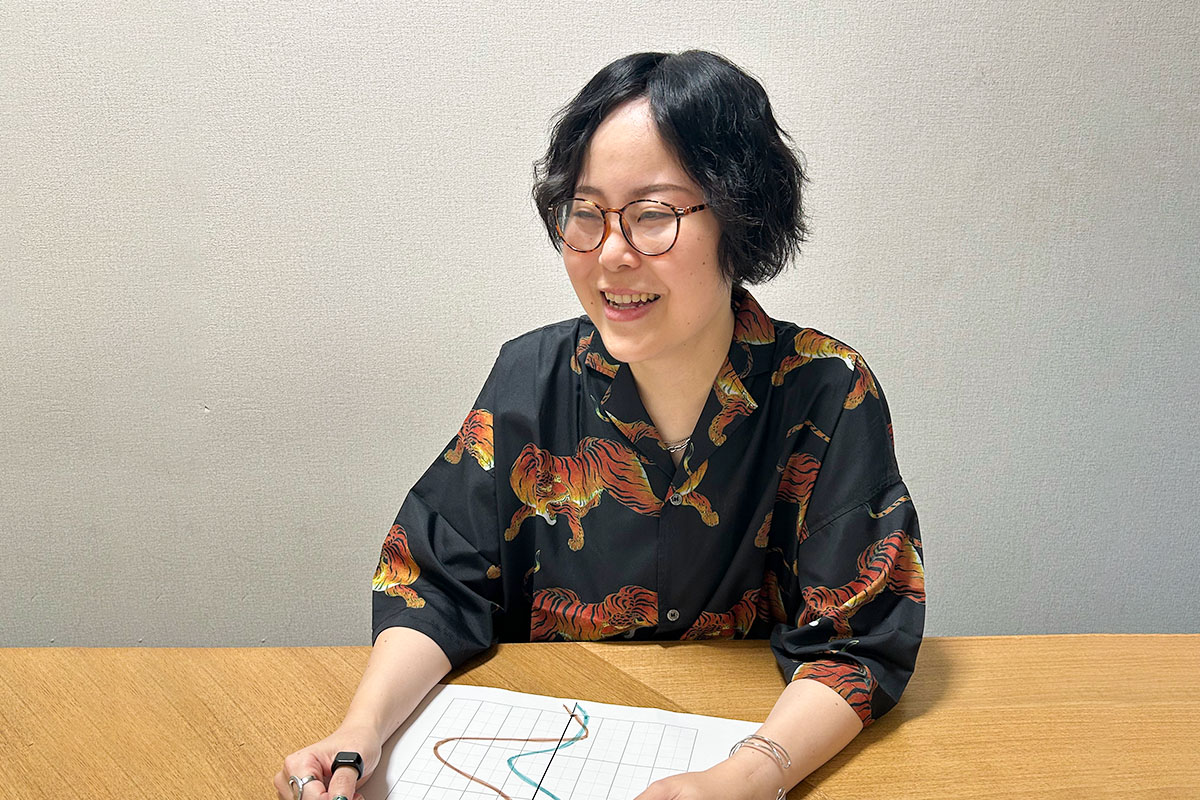
今は女性であることに対し、YESかNOかと言われたら「YES」であると言えるとおっしゃるまりぃさん。しかし、そこにはグラデーションがあるということをお話しいただきました。
「女性という集団に所属している」という気持ちがあるということは、自認としては女性というご認識なのでしょうか?
一時期はノンバイナリーがしっくりくるのかなと考えていたのですが、今は『女性ですか』と聞かれて『はい』と答えることに違和感はありません。ただ、女性ですと言った時に色々なものがついてくることが負担ではあります。『女性ってこういうもの好きだよね』などの押し付けは共感できないので性別を選ぶ場合は「その他」を選択するようにしています。
女性と言われれば女性なのですが、100%女性かと言われると悩んでしまう具合で、かと言ってノンバイナリーという性別の捉え方はしていないという曖昧な状況です。
例えば、上の世代からみた私は『若い女』というカテゴライズになってしまうことが良くも悪くもあるじゃないですか。 私はそのカテゴリーに属することが嫌であることと同時に申し訳ない部分もありました。私は”若い女性”というカテゴリーに付随する特性や期待されている役割(献身性やきめ細やかさや華やかさなど)を全く持っていないと感じていました。接待でクライアントと一緒に飲みに行くとなった時に”若い女性社員”が接待要員になる流れが多く、例に漏れず誘われた時は、『私で良いんですか?』と感じることはありました。その時は自分を女性と捉えることが、嫌というよりも申し訳ないと感じていました。
性自認よりも世間の女性のラベリングにギャップがあるというイメージでしょうか?
そうですね。世の中に求められているイメージとのギャップがあるイメージです。『女性ならではの意見を聞きましょう』や『これ、女性の目線としてどうですか?』と意見を求められると、私はそんな女性を代表するような、標準的なところにいないと考えています。
30代になってくるとその”若い女性”というカテゴリーからだんだん抜けていって、そこまで露骨では無いですが、飲み会に接待要員として入ることも少なくなり申し訳ないと感じることも少なくなっていきました。それはそれで別の問題がある気はするのですが、次世代が”若い女性”の役割を押し付けられているところを見ると、ちょっと思うところはあります。
まさに性自認に違和感がなくても、その自認には振り幅があるということですよね。過去、振るまいも性自認が揺れていていることで悩みはありましたか?
恋愛のところで、相手の性別によって自分のポジションがものすごく変わってしまう部分はあまり良くないと感じています。性別なんて関係ないと思っているはずなのに、自分自身はこんなにも露骨に態度を変えていて、しかもそれが性自認ではなくて相手の性別ではっきり態度が変わってしまい、どうすることもできないというところで悩んでいるかもしれないですね。友達同士であれば相手がノンバイナリーということでも自分の振るまいを相手の性別で切り替えるというところは少ないのですが恋愛関係となるとそのようには行かないんです。
その悩みは誰かと共有していますか?
こんなふうにはっきり言語化したことは無いです。そういう話題になった時に考えや思いを話すことはありつつも、じっくり話さないとよく分かってもらえない話であるし、変に伝わって相手に曲解されたり、相手を傷つけたりすると困るので、あまりちゃんと話すことは少ないですね。大前提として、性のゆらぎという話ができる人じゃないと話さないです。
また、性的マイノリティの人に話すことも多少のハードルがあります。説明できる十分な時間があったり、そういうことに理解のある人だと話せるのですが、例えば性別が女性ですごくボーイッシュな人に対しても、『私はあなたを性別で判断していて、あなたを女性として接しているんですよ』と伝えているようなものだから、とても失礼と感じて言えないなと思うんです。
世の中のラベリングやジェンダー、セクシャリティの問題に関して思うことはありますか?
あります。例えば私の職場では管理職のほとんどが男性で、悪気はないものの会議の場で『女性視点からの意見をください』と意見が求められることがあります。そういうときは、『別に私の意見が女性全体の意見じゃないんですけど』と前置きをして話したり、伝えられそうな相手であれば『さっきの発言、良くないんじゃないですか?』と伝えるようにしています。最近は気づいたタイミングで言うようにはしていますが、もちろん相手を否定したいわけではないですし、敵対したいわけではないので様子を見て意見を述べています。
ラベリングやジェンダーロールの問題は地域差や世代差もあると思っていて、私の地元では男性/女性の役割の差がかなり残っています。帰省すると男性の親族はゆっくりしているのに女性はキッチンに入ったり、お茶を出したりしています。不文律でそのような決まりがあるんです。この構図に関しては男性と女性の収入格差とかが如実に影響しているのかもしれません。帰るたびにキッチンに立たされるのでこんなところでは生きていけないと感じてしまう部分もありますね。社会を変えていきたいです。
大好きな漫画から感じたことなどはありますか?
世代差でいうと、私が幼少期の時はセーラームーンも好きで、ウラヌス(※セーラー戦士の中でも中性的なキャラクター)や少女革命ウテナ(※主人公ウテナの一人称が『僕』だったり、同性愛を感じる表現がある)など性自認、性表現や性的指向が曖昧なキャラが登場していました。CLAMPさんの作品は意識的にそのジェンダーの概念を崩そうとしているものが多い印象です。
ありがとうございます。最後に自分の性のあり方に悩んでいる人、迷っている人に伝えたいことはありますか?
私も20代のときは本当に自分が何が好きなのかよくわからないという状況で、試してみようとすると極端に女性性にふれたり、男性性にふれたりしていましたが、それは割と良くあることで、30代になると落ち着いてきましたし、いい意味で他人のことを気にしないようになってきました。自分が思ってるほど、周りの人は自分に関心ないということも分かってきます。
また、ジェンダーロールの部分にはなりますが、地方の差や家庭、個人の差はあるので逃げられる環境であれば逃げてしまっても良いと思います。私も逃げてきたうちの一人です。
人との関わりや自分のあり方という面に関しては、あるとき読んだ平野啓一郎さんの本で『分人主義』という考え方にすごく救われました。それは、人は一つの人格で生きているわけではなくて、職場での自分、家族の中での自分、恋人といるときの自分、独りでいるときの自分…など、“分人”を持っていて、使い分けているという考え方です。自分を一つのラベルにまとめようとしたり、振るまいに一貫性がなくても良くて、自分の中の分人のパーセンテージを変えながら調整していくという内容があり、それがすごく自然なことなんだと思えました。
仮に何か失敗したとしても、この人との“分人”は失敗しちゃったけど、自分には他にも分人がいると思えたら、100%失敗しているわけではないので少しだけ気持ちが楽になるかもしれません。仮に50%を占めている分人が失敗したとしても、また他の分人のパーセンテージ調整をしていけば良いだけです。平野啓一郎さんの本、ぜひ読んでみてください。
